SEの1年目~3年目までの過ごし方

システムエンジニアのスタートダッシュ
システムエンジニアとしてのキャリアをスタートさせることは、多くの可能性と挑戦が待ち受ける旅の始まりです。

新しい環境、技術、そして人間関係の中で、どのようにスタートダッシュを決めるかがその後の成長に大きく影響します。
SEとして成功するためには、技術力だけでなく、コミュニケーション能力やプロジェクト管理能力など、多面的なスキルが求められます。
最初の3年間は特に重要で、この期間にどれだけ成長できるかが、その後のキャリアの方向性を決める鍵となります。
まずは基礎をしっかりと固め、積極的に学び、失敗を恐れずにチャレンジする姿勢が大切です。
また、周囲の先輩SEから学ぶ謙虚さと、自分の意見を持つ自主性のバランスを取ることも重要です。
この記事では、SEとしての最初の3年間をどのように過ごすべきか、各年次ごとの目標や学ぶべきことを詳しく解説します。

新しい環境、技術、そして人間関係の中で、どのようにスタートダッシュを決めるかがその後の成長に大きく影響します。
SEとして成功するためには、技術力だけでなく、コミュニケーション能力やプロジェクト管理能力など、多面的なスキルが求められます。
最初の3年間は特に重要で、この期間にどれだけ成長できるかが、その後のキャリアの方向性を決める鍵となります。
まずは基礎をしっかりと固め、積極的に学び、失敗を恐れずにチャレンジする姿勢が大切です。
また、周囲の先輩SEから学ぶ謙虚さと、自分の意見を持つ自主性のバランスを取ることも重要です。
この記事では、SEとしての最初の3年間をどのように過ごすべきか、各年次ごとの目標や学ぶべきことを詳しく解説します。
SEの1年目~3年目までの過ごし方
新人SEから中堅SEへと成長する最初の3年間は、技術的基盤を固めるとともに、ビジネススキルを身につけていく重要な時期です。
年次ごとに適切な目標を設定し、段階的にスキルアップしていくことが大切です。
ここでは、1年目から3年目までの各段階で意識すべきポイントを解説します。

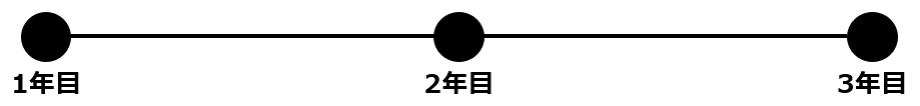 入社1年目は、SEとしての基礎を固める時期です。
入社1年目は、SEとしての基礎を固める時期です。
この時期に最も重要なのは、基本的な技術スキルの習得とビジネスマナーの理解です。
新入社員として入社した場合は、基本的には集団研修から始まります。
そこでシステムエンジニアとしての基本的な技術やビジネスマナーを学ぶことになるでしょう。
研修が終わったら、実際に部署へ配属されていくことになります。
ここからシステムエンジニアとしての仕事が始まります。
まずは与えられた業務を確実にこなすことに集中しましょう。
プログラミング言語やデータベース、ネットワークなどの基礎知識を身につけることが最優先事項です。
また、ビジネス文書の書き方や報告・連絡・相談のタイミングなど、社会人としての基本的なスキルも習得する必要があります。
おそらく最初はがわからないことだらけになってしまうと思います。
分からないことは積極的に質問し、メモを取る習慣をつけることが大切です。
1年目の時は質問をしても許される時期です。怒る先輩がいればその人がおかしいと思っていいです。
この時期は「吸収の時期」と考えて、先輩の仕事の進め方や問題解決のアプローチ方法を観察し、学ぶことを心がけましょう。
先輩の真似をするうちに仕事の仕方も覚えて行くことができます。
特にメールはCCに入れてもらって、書き方を完全に真似してしまいましょう。
一から自分なりのメールの書き方を考える必要はありません。
また、チームの一員としての自覚を持ち、「報連相」を心がけるなど、信頼される人材になることを意識しましょう。
「任されたタスクでわからないところがある」「タスクが期限より遅れそう」など、できるだけ早く報連相をしましょう。
早めに報告されるだけでも、放置してタスクを投げ出す人ではないとわかるので、信頼を得ることができます。
1年目の終わりには、基本的な開発環境での作業に慣れ、簡単なプログラミングやテスト業務を自力で行えるようになることが目標です。

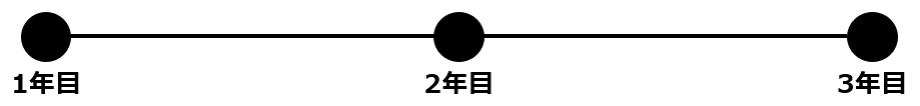 入社2年目になると、基本的な業務は一人で遂行できるようになり、より高度な業務にチャレンジする時期です。
入社2年目になると、基本的な業務は一人で遂行できるようになり、より高度な業務にチャレンジする時期です。
この時期の目標は、専門性の発芽とチーム内での価値提供です。
特定の技術領域や業務領域に対して多少の知識を持ち始め、小規模な設計や実装を任されるようになるでしょう。
チーム内でのコミュニケーションもより積極的になり、自分の意見や提案を述べる機会も増えてきます。
この時期は「実践の時期」であり、1年目で学んだことを実際のプロジェクトで活かし、経験値を積み重ねることが重要です。
業務の仕方を覚え始めたら、業務効率化のための工夫など、仕事の速度を上げる意識を持ちましょう。
単純ですが、ショートカットキーを覚えることはこれからのシステムエンジニア人生においてかなり有用です。
大げさに言うと、マウスをほとんど使わず、キーボードだけでも操作ができるレベルになると、PC操作が各段に早くなります。
2年目の終わりには、小規模な機能の設計から実装、テストまでを一人で完結できるようになるレベルを目指します。
自身で開発環境などを使って、検証を行い、設計し、実装を行い、テストまでを簡潔できれば2年目のシステムエンジニアとしては十分です。

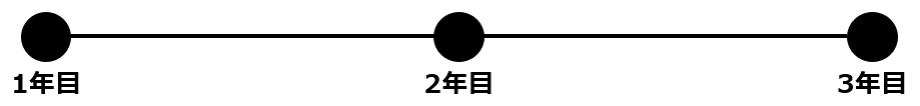 入社3年目は、2年めに引き続きSEとしての基礎固めをしつつ、より責任ある立場に挑戦し始める時期です。
入社3年目は、2年めに引き続きSEとしての基礎固めをしつつ、より責任ある立場に挑戦し始める時期です。
この時期の目標は、リーダーシップへの挑戦と専門性の確立です。
少し大き目のタスクを任され、1人~2人のメンバーを持ちタスクの指示をしながら進めていくような機会が増えてきます。
技術面では、特定の分野については1人前として認められ始め、ある程度難しい問題の解決や最適な実装方法の提案ができるようになっていく時期です。
また、顧客とのコミュニケーションの場に同席し、ビジネス面での理解も深めていく時期です。
直接、顧客への説明などを経験し、自身の考えを社内ではなく、社外の顧客相手にも伝えるということを意識し始める時期です。
顧客から見ると3年目などの年次は関係なく、お金を払っているプロのシステムエンジニアとして扱われます。
社外の人間へ伝えるということを意識し始め、資料の作り方、説明の仕方、内容への責任など考え方がよりプロとして変わっていくことができるでしょう。
この時期は「貢献の時期」であり、チームや組織に対して明確な価値を提供することが求められます。
プロジェクト全体を見渡す視点を持ち、上流工程(要件定義や設計)にも積極的に関わるようにしましょう。
3年目の終わりには、中規模な機能の設計・実装をメンバーとともに任され、技術選定や実装方針の決定に関与できるレベルを目指すとよいでしょう。
年次ごとに適切な目標を設定し、段階的にスキルアップしていくことが大切です。
ここでは、1年目から3年目までの各段階で意識すべきポイントを解説します。
システムエンジニア ~1年目~

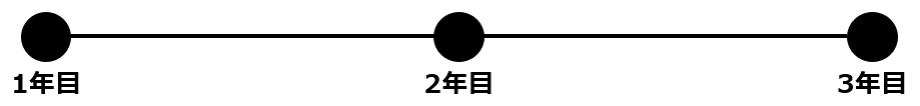
この時期に最も重要なのは、基本的な技術スキルの習得とビジネスマナーの理解です。
新入社員として入社した場合は、基本的には集団研修から始まります。
そこでシステムエンジニアとしての基本的な技術やビジネスマナーを学ぶことになるでしょう。
研修が終わったら、実際に部署へ配属されていくことになります。
ここからシステムエンジニアとしての仕事が始まります。
まずは与えられた業務を確実にこなすことに集中しましょう。
プログラミング言語やデータベース、ネットワークなどの基礎知識を身につけることが最優先事項です。
また、ビジネス文書の書き方や報告・連絡・相談のタイミングなど、社会人としての基本的なスキルも習得する必要があります。
おそらく最初はがわからないことだらけになってしまうと思います。
分からないことは積極的に質問し、メモを取る習慣をつけることが大切です。
1年目の時は質問をしても許される時期です。怒る先輩がいればその人がおかしいと思っていいです。
この時期は「吸収の時期」と考えて、先輩の仕事の進め方や問題解決のアプローチ方法を観察し、学ぶことを心がけましょう。
先輩の真似をするうちに仕事の仕方も覚えて行くことができます。
特にメールはCCに入れてもらって、書き方を完全に真似してしまいましょう。
一から自分なりのメールの書き方を考える必要はありません。
また、チームの一員としての自覚を持ち、「報連相」を心がけるなど、信頼される人材になることを意識しましょう。
「任されたタスクでわからないところがある」「タスクが期限より遅れそう」など、できるだけ早く報連相をしましょう。
早めに報告されるだけでも、放置してタスクを投げ出す人ではないとわかるので、信頼を得ることができます。
1年目の終わりには、基本的な開発環境での作業に慣れ、簡単なプログラミングやテスト業務を自力で行えるようになることが目標です。
システムエンジニア ~2年目~

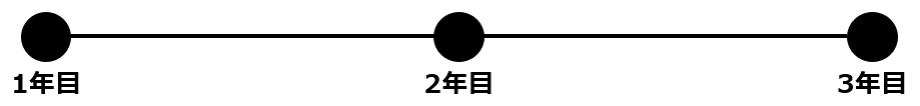
この時期の目標は、専門性の発芽とチーム内での価値提供です。
特定の技術領域や業務領域に対して多少の知識を持ち始め、小規模な設計や実装を任されるようになるでしょう。
チーム内でのコミュニケーションもより積極的になり、自分の意見や提案を述べる機会も増えてきます。
この時期は「実践の時期」であり、1年目で学んだことを実際のプロジェクトで活かし、経験値を積み重ねることが重要です。
業務の仕方を覚え始めたら、業務効率化のための工夫など、仕事の速度を上げる意識を持ちましょう。
単純ですが、ショートカットキーを覚えることはこれからのシステムエンジニア人生においてかなり有用です。
大げさに言うと、マウスをほとんど使わず、キーボードだけでも操作ができるレベルになると、PC操作が各段に早くなります。
2年目の終わりには、小規模な機能の設計から実装、テストまでを一人で完結できるようになるレベルを目指します。
自身で開発環境などを使って、検証を行い、設計し、実装を行い、テストまでを簡潔できれば2年目のシステムエンジニアとしては十分です。
システムエンジニア ~3年目~

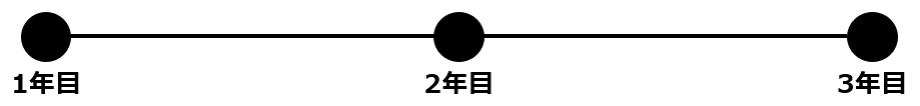
この時期の目標は、リーダーシップへの挑戦と専門性の確立です。
少し大き目のタスクを任され、1人~2人のメンバーを持ちタスクの指示をしながら進めていくような機会が増えてきます。
技術面では、特定の分野については1人前として認められ始め、ある程度難しい問題の解決や最適な実装方法の提案ができるようになっていく時期です。
また、顧客とのコミュニケーションの場に同席し、ビジネス面での理解も深めていく時期です。
直接、顧客への説明などを経験し、自身の考えを社内ではなく、社外の顧客相手にも伝えるということを意識し始める時期です。
顧客から見ると3年目などの年次は関係なく、お金を払っているプロのシステムエンジニアとして扱われます。
社外の人間へ伝えるということを意識し始め、資料の作り方、説明の仕方、内容への責任など考え方がよりプロとして変わっていくことができるでしょう。
この時期は「貢献の時期」であり、チームや組織に対して明確な価値を提供することが求められます。
プロジェクト全体を見渡す視点を持ち、上流工程(要件定義や設計)にも積極的に関わるようにしましょう。
3年目の終わりには、中規模な機能の設計・実装をメンバーとともに任され、技術選定や実装方針の決定に関与できるレベルを目指すとよいでしょう。
学ぶべきこと
SEとしての最初の3年間で学ぶべきことは多岐にわたります。
大きく分けると、技術スキル、ビジネススキル、ヒューマンスキルの3つの領域があります。
これらのスキルはすべて一度に身につくものではなく、日々の業務の中で意識的に実践し、振り返りを行うことで徐々に向上していきます。
また、業界や技術の動向にアンテナを張り、常に学び続ける姿勢を持つことも重要です。
変化の激しいIT業界では、学習を止めた瞬間に価値を失うリスクがあることを忘れないようにしましょう。
大きく分けると、技術スキル、ビジネススキル、ヒューマンスキルの3つの領域があります。
技術スキル
技術スキルとしては、プログラミング言語(Java、Python、JavaScript等)、データベース設計と操作、ネットワークの基礎知識、システム設計の基本原則などが挙げられます。
これらの技術スキルは、配属された部署によって変わることもあります。
開発をメインとする部署では、プログラミング言語やデータベースのテーブル設計などの基礎を学んでいくことになります。
インフラエンジニアとなれば、サーバ構築、ネットワーク、データベースなどを学んでいくことになるでしょう。
また、共通として開発手法(ウォーターフォール、アジャイル等)や、バージョン管理ツール(Git等)、CI/CDといった開発環境に関する知識も重要です。
これらの技術スキルは、配属された部署によって変わることもあります。
開発をメインとする部署では、プログラミング言語やデータベースのテーブル設計などの基礎を学んでいくことになります。
インフラエンジニアとなれば、サーバ構築、ネットワーク、データベースなどを学んでいくことになるでしょう。
また、共通として開発手法(ウォーターフォール、アジャイル等)や、バージョン管理ツール(Git等)、CI/CDといった開発環境に関する知識も重要です。
ビジネススキル
ビジネススキルとしては、要件定義の方法、見積もりの考え方、プロジェクト管理の基礎、ドキュメンテーションスキルなどが必要になります。
特に、顧客の真のニーズを引き出す力や、技術的な内容を非エンジニアにも分かりやすく説明する能力は、SEとして長く活躍するために欠かせません。
特に、顧客の真のニーズを引き出す力や、技術的な内容を非エンジニアにも分かりやすく説明する能力は、SEとして長く活躍するために欠かせません。
ヒューマンスキル
ヒューマンスキルとしては、コミュニケーション能力、チームワーク、問題解決能力、時間管理能力などが重要です。
特に、複数の関係者との調整やプロジェクト内での衝突解決など、「人」に関わる課題解決能力は、技術力と同等かそれ以上に価値があります。
また、自己管理能力やストレス管理能力も、長期的なキャリア構築には欠かせません。
特に、複数の関係者との調整やプロジェクト内での衝突解決など、「人」に関わる課題解決能力は、技術力と同等かそれ以上に価値があります。
また、自己管理能力やストレス管理能力も、長期的なキャリア構築には欠かせません。
これらのスキルはすべて一度に身につくものではなく、日々の業務の中で意識的に実践し、振り返りを行うことで徐々に向上していきます。
また、業界や技術の動向にアンテナを張り、常に学び続ける姿勢を持つことも重要です。
変化の激しいIT業界では、学習を止めた瞬間に価値を失うリスクがあることを忘れないようにしましょう。
まとめ
SEとしての最初の3年間は、技術的な基礎固めから始まり、徐々に専門性を高め、チームへの貢献度を増していく発展的な期間です。
1年目は基本スキルの習得と社会人としての基礎を固め、2年目は専門性の芽を育てながらチーム内での価値提供を意識し、3年目はリーダーシップを発揮しながら明確な専門分野を確立していくことが理想的なキャリアパスと言えるでしょう。
この3年間で身につけるべきスキルは、技術面だけでなく、ビジネス面、ヒューマンスキル面と多岐にわたります。
しかし、すべてを完璧に習得する必要はなく、自分の強みを見つけ、それを活かせる分野で深い専門性を持つことが重要です。
SEとしてのキャリアは長期的な視点で考えるべきものであり、最初の3年間はその土台を築く期間と捉えましょう。
日々の小さな成長の積み重ねが、将来の大きな飛躍につながります。
失敗を恐れず、常に学び続ける姿勢を持ち、周囲の人々との良好な関係を築きながら、自分らしいSEとしてのキャリアを歩んでいくことを願っています。
最後に、技術の世界は常に変化していますが、「ユーザーに価値を提供する」というSEの本質は変わりません。
技術はあくまで手段であり、それを通じて人々や社会に貢献することがSEとしての真の喜びであることを忘れないでください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
1年目は基本スキルの習得と社会人としての基礎を固め、2年目は専門性の芽を育てながらチーム内での価値提供を意識し、3年目はリーダーシップを発揮しながら明確な専門分野を確立していくことが理想的なキャリアパスと言えるでしょう。
この3年間で身につけるべきスキルは、技術面だけでなく、ビジネス面、ヒューマンスキル面と多岐にわたります。
しかし、すべてを完璧に習得する必要はなく、自分の強みを見つけ、それを活かせる分野で深い専門性を持つことが重要です。
SEとしてのキャリアは長期的な視点で考えるべきものであり、最初の3年間はその土台を築く期間と捉えましょう。
日々の小さな成長の積み重ねが、将来の大きな飛躍につながります。
失敗を恐れず、常に学び続ける姿勢を持ち、周囲の人々との良好な関係を築きながら、自分らしいSEとしてのキャリアを歩んでいくことを願っています。
最後に、技術の世界は常に変化していますが、「ユーザーに価値を提供する」というSEの本質は変わりません。
技術はあくまで手段であり、それを通じて人々や社会に貢献することがSEとしての真の喜びであることを忘れないでください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
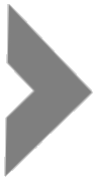

 前の記事へ
前の記事へ