SEとSESってどんな違いがあるの?

システムエンジニアリングサービス(SES)とは?
システムエンジニアという仕事について調べているとSESというキーワードを見かけていませんか?
このSESというのはシステムエンジニアリングサービスの略になっております。
名前だけ聞いてもちょっとわからないですよね
要はシステムエンジニアを色々な会社に貸し出しを行うサービスのことをSESと呼びます。

SESは多くのシステムエンジニアを保有しており、必要とする会社へシステムエンジニアの技術力を提供することで利益を得るような業種です。
上の図で「クライアント」と書いている企業は、IT技術に疎い企業もあれば実はSIerと呼ばれるシステム構築を専門とする会社も含まれています
この業態を具体的に理解するために、何故このようなSESが必要になるかというところから説明していきます。
IT技術に疎い一般企業が新たにシステム構築を行いとなったときに、システムエンジニアの会社へ構築を依頼します。
これはSEってどんな仕事?のページでも解説しましたね。
この時に依頼を受ける会社は一般にSIerと呼ばれる会社になります。
SIerはシステムインテグレーターの略でエスアイヤーやエスアイアーと呼びます。
このSIerがどのようなシステムを構築したいのか、どういったシステム構成(アーキテクチャと言います。)とするかを依頼者と会話しながら検討してきます。
この時点では、必要なIT技術がわからない状態なのです。

お客様とシステムのイメージをすり合わせが進んだ時に初めて、必要となる技術が判明します。
また、SIerには多くの企業からシステム構築の依頼が舞い込みますので、その時に受注している案件次第で必要なIT技術が変わってきてしまうのです。
最近は使われなくなった古い技術が必要となることもあるため、1つの会社内にあまり使うことのない技術を習得したエンジニアを常駐させておくことは難しいのです。
そのため、必要になときに必要な技術を持つシステムエンジニアの力を借りることのできるSESという業態が出てきたのです。

このようにSESは、IT技術に疎い一般企業からシステム構築を専門とするようなSIer企業まで幅広くIT技術のエンジニアを提供する業態と言えます。
このSESというのはシステムエンジニアリングサービスの略になっております。
名前だけ聞いてもちょっとわからないですよね
要はシステムエンジニアを色々な会社に貸し出しを行うサービスのことをSESと呼びます。

SESは多くのシステムエンジニアを保有しており、必要とする会社へシステムエンジニアの技術力を提供することで利益を得るような業種です。
上の図で「クライアント」と書いている企業は、IT技術に疎い企業もあれば実はSIerと呼ばれるシステム構築を専門とする会社も含まれています
この業態を具体的に理解するために、何故このようなSESが必要になるかというところから説明していきます。
IT技術に疎い一般企業が新たにシステム構築を行いとなったときに、システムエンジニアの会社へ構築を依頼します。
これはSEってどんな仕事?のページでも解説しましたね。
この時に依頼を受ける会社は一般にSIerと呼ばれる会社になります。
SIerはシステムインテグレーターの略でエスアイヤーやエスアイアーと呼びます。
このSIerがどのようなシステムを構築したいのか、どういったシステム構成(アーキテクチャと言います。)とするかを依頼者と会話しながら検討してきます。
この時点では、必要なIT技術がわからない状態なのです。

お客様とシステムのイメージをすり合わせが進んだ時に初めて、必要となる技術が判明します。
また、SIerには多くの企業からシステム構築の依頼が舞い込みますので、その時に受注している案件次第で必要なIT技術が変わってきてしまうのです。
最近は使われなくなった古い技術が必要となることもあるため、1つの会社内にあまり使うことのない技術を習得したエンジニアを常駐させておくことは難しいのです。
そのため、必要になときに必要な技術を持つシステムエンジニアの力を借りることのできるSESという業態が出てきたのです。

このようにSESは、IT技術に疎い一般企業からシステム構築を専門とするようなSIer企業まで幅広くIT技術のエンジニアを提供する業態と言えます。
ポイント!
SESは多種多様なシステムエンジニアを保有し、他の会社に貸し出しを行う業態のことです!
SIerとは?
比較元であるSIerについても説明していきます。
SIerとは、SEという職業をイメージした時に大多数の人が想像するようなシステム構築をメインとして請け負う会社のことを言います。
ITに詳しくないお客様からシステムの構築や運用までを含むシステム全般の業務を行っています。
上流工程と呼ばれる顧客の業務分析を行い、システムによる課題解決に向けたコンサルティング業務からまでを含むこともあり、まさにシステムエンジニアという職業でイメージする業務となります。
システム構築において、全ての工程を請けおえることを「ワンストップサービス」なんて言い方をしたりします。

お客様からのシステム構築依頼を直接請ける1次請けとなることが多く、どのようなシステムを作るかを計画・管理していくことから始まります。
その後、設計や構築、運用までを責任持って進めていくような会社です。
お客様との折衝交渉が多く発生するため、コミュニケーション能力とIT技術力の両方を兼ね備えて置く必要があります。
ただ、どちらかというとコミュニケーション能力のほうが重要となる場面も多いため、SIerへは文系大学から入社する人も多くいるのが特徴です。
SIerとは、SEという職業をイメージした時に大多数の人が想像するようなシステム構築をメインとして請け負う会社のことを言います。
ITに詳しくないお客様からシステムの構築や運用までを含むシステム全般の業務を行っています。
上流工程と呼ばれる顧客の業務分析を行い、システムによる課題解決に向けたコンサルティング業務からまでを含むこともあり、まさにシステムエンジニアという職業でイメージする業務となります。
システム構築において、全ての工程を請けおえることを「ワンストップサービス」なんて言い方をしたりします。

お客様からのシステム構築依頼を直接請ける1次請けとなることが多く、どのようなシステムを作るかを計画・管理していくことから始まります。
その後、設計や構築、運用までを責任持って進めていくような会社です。
お客様との折衝交渉が多く発生するため、コミュニケーション能力とIT技術力の両方を兼ね備えて置く必要があります。
ただ、どちらかというとコミュニケーション能力のほうが重要となる場面も多いため、SIerへは文系大学から入社する人も多くいるのが特徴です。
SE(SIer)となにが違うの?
ここまででSIerやSESの業態について説明してきました。
では、具体的にどういった違いがあるのでしょうか?
答えとしては、SESはSEの働き方の一種と言えるでしょう。

SEというのは今までの説明にあったとおり、技術という側面でも多用な人材がいます。
そして、別の見方として働き方にも、種類があるのです。
SIerとして、お客様と直接交渉しながら、1次請けとしてシステム構築を責任もって管理・監督していくような働き方もあります。
SESとして、技術のスペシャリストとして、色々な案件を渡り歩く技術人になるような働き方もあります。
また、別の働き方としてはフリーランスとして、全て自分一人で行うような働き方だってできます。
では、具体的にどういった違いがあるのでしょうか?
答えとしては、SESはSEの働き方の一種と言えるでしょう。

SEというのは今までの説明にあったとおり、技術という側面でも多用な人材がいます。
- サーバに特化したエンジニア
- データベースに特化したエンジニア
- ネットワークに特化したエンジニア
- プログラム開発に特化したエンジニア
そして、別の見方として働き方にも、種類があるのです。
SIerとして、お客様と直接交渉しながら、1次請けとしてシステム構築を責任もって管理・監督していくような働き方もあります。
SESとして、技術のスペシャリストとして、色々な案件を渡り歩く技術人になるような働き方もあります。
また、別の働き方としてはフリーランスとして、全て自分一人で行うような働き方だってできます。
ポイント!
SESというのは、システムエンジニアの働き方の1種である。
ITの技術力を色々な会社へ提供するようなかかわり方をする業態です。

ITの技術力を色々な会社へ提供するようなかかわり方をする業態です。

SESの働き方のイメージ
SESの場合、様々な会社へ技術者を提供するような業態と説明してきました。
なので、提供先がないような状況も発生します。
そのような状態を「待機」と呼びます。

もちろん待機状態でも、SESの会社に雇用されている従業員であることは変わりませんので、お給料は支払われます。
ただ、会社としてはエンジニアを貸し出さないと利益が出ない業態ですので、何とかして現場を探します
ということで、SESのシステムエンジニアは現場を探すところから始まります。
システムエンジニアを必要としていそうな会社にアポイントをとって面接のような打ち合わせをすることもあります。
「私はこのような技術を持っています!」とアピールして依頼があれば、案件に参画するような流れです。

現場が決まったら、その会社へ技術力を提供するために案件に参画して仕事を行います。
仕事の内容は参画した案件によって変わってきますので、柔軟に対応するスキルが必要になってきます。
このように自分の技術力が必要な現場を探して、色々な案件を渡り歩くような仕事の仕方となります。
なので、提供先がないような状況も発生します。
そのような状態を「待機」と呼びます。

もちろん待機状態でも、SESの会社に雇用されている従業員であることは変わりませんので、お給料は支払われます。
ただ、会社としてはエンジニアを貸し出さないと利益が出ない業態ですので、何とかして現場を探します
ということで、SESのシステムエンジニアは現場を探すところから始まります。
システムエンジニアを必要としていそうな会社にアポイントをとって面接のような打ち合わせをすることもあります。
「私はこのような技術を持っています!」とアピールして依頼があれば、案件に参画するような流れです。

現場が決まったら、その会社へ技術力を提供するために案件に参画して仕事を行います。
仕事の内容は参画した案件によって変わってきますので、柔軟に対応するスキルが必要になってきます。
- 客先常駐 or リモートワーク
- システム開発 or システム運用
- 設計書作成
- 折衝交渉
このように自分の技術力が必要な現場を探して、色々な案件を渡り歩くような仕事の仕方となります。
SESとして働くメリット/デメリット
それではシステムエンジニアの働き方としてSESを業態としている会社で働くメリットとデメリットを説明します。
SESでは、現場がコロコロ変わってしまうという点からメリット・デメリットが発生しやすいです。
現場の環境に慣れてきたと思ったころに別の現場に異動になってしまうことも多々としてあります。
また、現場によっては苦手な人のいる場所もあるでしょう。
そのような場所に参画してしまうリスクもありますが、現場を変えやすいので別の場所へ異動させてもらうことで避けやすいという一面もあります。
そして一番のデメリットは給与水準が低めなところでしょう。
SESは業態として、システムを必要とするお客様から直接依頼を受ける一次請けとなりづらいです。
基本的には一次請けとなった企業から技術力の提供として、二次請け、三次請けとなるため、案件規模自体が小さくなりがちで利益が少なくなります。
会社の利益が少ないということは従業員に支払う給料も高くはできず、薄給となる傾向にあります。
ただ、需要の高い技術を身に着け、1次請けが行うような要件定義等の工程も遂行することができるような上級のSESとなれば、給与が十分に上がる可能性もあります。
現在、システムエンジニアの業界は人手不足ということもあり、能力の高いエンジニアにはある程度の金額を払ってでも確保したいという傾向になりつつあります。
 メリット
メリット
- 多種多様な案件を経験することができる
- 責任範囲が狭い
- 技術のスペシャリストを目指しやすい
- 未経験でも就職しやすい
 デメリット
デメリット
- 案件により当たり外れの幅が大きい
- 自社からのサポートを受けづらい
- 技術ばかりで要件定義などの工程を経験できない
- 給与水準が低め
- 現場がよく変わるので現場ルールへの適応力が必要
SESでは、現場がコロコロ変わってしまうという点からメリット・デメリットが発生しやすいです。
現場の環境に慣れてきたと思ったころに別の現場に異動になってしまうことも多々としてあります。
また、現場によっては苦手な人のいる場所もあるでしょう。
そのような場所に参画してしまうリスクもありますが、現場を変えやすいので別の場所へ異動させてもらうことで避けやすいという一面もあります。
そして一番のデメリットは給与水準が低めなところでしょう。
SESは業態として、システムを必要とするお客様から直接依頼を受ける一次請けとなりづらいです。
基本的には一次請けとなった企業から技術力の提供として、二次請け、三次請けとなるため、案件規模自体が小さくなりがちで利益が少なくなります。
会社の利益が少ないということは従業員に支払う給料も高くはできず、薄給となる傾向にあります。
ただ、需要の高い技術を身に着け、1次請けが行うような要件定義等の工程も遂行することができるような上級のSESとなれば、給与が十分に上がる可能性もあります。
現在、システムエンジニアの業界は人手不足ということもあり、能力の高いエンジニアにはある程度の金額を払ってでも確保したいという傾向になりつつあります。
まとめ
システムエンジニアと一言で言っても入社した会社の業態によっては、働き方や携わる領域が大きく変わります。
これから就職活動や転職するようであれば、SIerのような働き方がしたいのか、SESのような働き方がしたいのかは一度検討しておくことをお勧めします。
どちらのほうが優れているということではなく、自身の性格や重視する場所の違いになります。
自分の希望と齟齬がある状態だと精神的に負担がかかったり、長続きしないような結果にもなりかねませんからね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
これから就職活動や転職するようであれば、SIerのような働き方がしたいのか、SESのような働き方がしたいのかは一度検討しておくことをお勧めします。
どちらのほうが優れているということではなく、自身の性格や重視する場所の違いになります。
自分の希望と齟齬がある状態だと精神的に負担がかかったり、長続きしないような結果にもなりかねませんからね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。

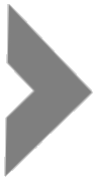

 前の記事へ
前の記事へ
 人気の記事
人気の記事